座禅会 柔軟な心で受け流す

4月に入りまして、気温がぐっと上がってまいりました。
境内は遅咲きの桜がたくさんきれいに咲いております。
さて、本日は、第2土曜日で、恒例の座禅会を開催いたしました。
このたびは、初参加の方を含め、16名の方がご参加くださいました。
初参加の方もたくさん来ていただき、ありがとうございました!

今回も、ソーシャルディスタンスを確保し、マスクを着用していただきました。
お経のほうも、参加者の皆様には黙読していただき、私はマイクで唱えさせていただきました。
そして、25分の座禅を2セットした後、マイクで、お話をさせていただきました。
本日のお話は、「風」の受け止め方のお話。
お釈迦様は法句経の中で「愚かな人」と対比させて「賢い人」についてこんな教えを説かれています。
「一つの岩の塊りが風に揺るがないように、賢者は非難と賞讃とに動じない。」
愚かな人は非難されれば怒り、賞讃されれば調子に乗ったりと、心がすぐ揺れ動いてしまいます。
お釈迦様は、心が安らかな賢者、仏さんとなった人の心を、どんな風にも揺るがない「岩」に例えました。
一方、お釈迦様のように坐禅の修行をして悟りを開いた禅僧も、仏さんの心を様々な禅語などで表現してきました。
江戸時代の禅僧、仙厓和尚は美濃国(今の岐阜県)に生まれ、禅の修行をして悟りを開きました。
その後、博多に移り、聖福寺の住職となり、禅の教えを庶民にも分かりやすい絵画などで表現しました。
その中に、「堪忍柳画賛 」という作品があります。柳の絵を描き、右に堪忍と書き、左にこんな賛をつけました。
「気に入らぬ風もあろうに柳かな」
心地よい風も吹けば、強風も吹く。柳は、気に入らぬ風が吹いても、枝をしなわせて受け流していると。
力を入れて我慢するのではなく、余計な力を抜いて、そのまま風を受けていく。
仙厓さんは、仏さんの心を「柳」に例え、人生での困難も自然体で受け止めていくと表現しました。
私達も、余計な力を抜いた「柳」のように柔軟な心で、一日一日を過ごしていきたいですね。
このような話をいたしました。
話が終わりますと、参加者の皆さんには、お茶とお菓子をお持ち帰りいただきました。
来月は新緑の季節、早咲きのアジサイの花の蕾がふくらんでくる頃です。
また、来月の坐禅会も是非お越しください!
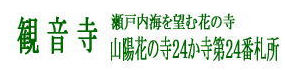

最近のコメント