座禅会 巌頭和尚まめ息災

立春を過ぎて、少しずつ春に向かう季節となりました。
寒さに耐えていた梅も、蕾が膨らんできております。

本日は、第2土曜日で、恒例の座禅会を開催いたしました。
初参加の方、2名を含め、14名の方がご参加くださいました。
まだまだお寒い中、ご参加くださいましてありがとうございました!

今回も、ソーシャルディスタンスを確保し、マスクを着用していただきました。
お経のほうも、参加者の皆様には黙読していただき、私はマイクで唱えさせていただきました。
そして、25分の座禅を2セットした後、マイクで、お話をさせていただきました。
本日のお話は、豆まきに因んで「まめ息災」のお話。
「まめ」も「息災」も健康、達者、無事といった意味があります。
さて、中国の唐の時代の禅僧に巌頭(がんとう)和尚という方がいます。
「臨済の喝、徳山の棒」と、臨済禅師と並び称された、徳山和尚の法を継いだ方です。
そんな巌頭和尚ですが、60歳の時に賊の手にかかり亡くなります。
江戸時代の白隠禅師は、15歳で出家し、19歳の時に巌頭和尚の最期について知ります。
10歳の頃にお寺で聞いた話によって、地獄を恐れ出家を志した白隠禅師は落胆しました。
巌頭和尚ほどの禅僧が賊に殺されてしまうのなら、自分は地獄からどうして逃れられようかと。
その後、24歳の時、徹夜で坐禅中に、遠くのお寺の朝の鐘を聞いて、悟りを開きました。
白隠禅師はこう叫んだといわれています。
「 巌頭和尚はまめ息災であったわい。巌頭和尚はまめ息災であったわい。」
坐禅で自分が無になった時に、鐘がゴーンと響いた瞬間、全てが自分という心境にたどり着き、
ここに生きた巌頭和尚がおるではないかと白隠禅師は気づかされたのではないでしょうか。
全ては縁でつながり、私達は縁によって生まれ、様々なご縁に支えられ生かされています。
亡くなれば、様々な命を生み出す大いなる命とも言うべき大自然に帰っていきます。
全てを自分と一体に感じて、自分の中に全てが詰まっていると感じる。
身近で亡くなった人も、生きている人達の中で生き続けていると私達も感じることがあります。
「巌頭和尚まめ息災」という気持ちで、これからの日々を生きていきたいですね。
このような話をいたしました。
お話の後、参加者の皆さんには、お茶とお菓子をお持ち帰りいただきました。
来月の座禅会は、早咲きの河津桜が開花している頃です。
是非また座禅会にご参加ください!
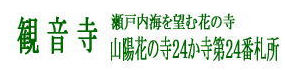

最近のコメント