座禅会 無心の働き
4月に入り、春本番です。境内の桜も次々に開花し、遅咲きの桜も間もなく開花します。
さて、第2土曜日の12日には、坐禅会が開かれ、21名様がご参加くださいました。
参加者の皆様、ありがとうございました!
25分の座禅を2セットして、茶話会。
このたびも、やまだ屋さんから施菓をいただきました。
いつもありがとうございます!
茶話会の話は、白隠禅師坐禅和讃の中の言葉、「無念の念を念として、謡うも舞うも法の声」。
無念の念、つまり、思わないで思うことをして、歌うことも踊ることも、仏さんの姿であると。
何も考えないのだけれど、しっかりとした働きがある、無心に働いているのが仏さんである。
無念の念で生きれば、歌うことでさえも踊ることでさえも、仏さんの姿といったことでしょう。
江戸幕末から明治にかけて活躍した方に山岡鉄舟がいました。
山岡鉄舟は、剣術・書道・禅の達人といわれておりました。
その鉄舟のもとに、三遊亭円朝という落語家が訪ねてきました。
すると、鉄舟は円朝にこう言いました。
「わしの小さい頃、お母さんが桃太郎の話をしてくれて、何度聞いても面白かった。だから、桃太郎の話を一席お願いしたい。」
円朝は桃太郎の話をしましたが、鉄舟は満足しません。
「全然面白くない。お母さんの方がずっと上手だった。だいたい、あんたは舌でしゃべるからいかん。」
家に帰った円朝は、鉄舟に言われた言葉が気になって仕方ありません。
後日、鉄舟のもとを再び訪ねて、「舌でしゃべらなければ、どうやってしゃべるのですか。」と聞きました。
鉄舟はこう答えました。
「そこだ。落語家は舌を無くしてしゃべらんといかん。役者は体を無くして演じなくてはダメだ。それには禅の修行が必要だ。だから、昔の名人は皆、禅の修行をしたものだ。あんたも禅をやってみるか。」
鉄舟のもとで数年間、禅の修行に励んだ円朝。
鉄舟は、「もう一回、桃太郎の話をやってみなさい。」と言いました。
そこで、円朝が桃太郎の話をすると、鉄舟は手を打って喜んで、「今日の桃太郎は生きておるぞ。」と円朝を大いにほめたそうです。
しゃべろうと舌を意識している間は、まだまだ本物ではない。しゃべろうと思わないで、桃太郎の登場人物になりきってしゃべってこそ、話が生き生きとしてくるのです。
日常生活でも、こうしようといった思いもなく、相手の気持ちになりきってこそ、相手の心を動かす働きが出てくるのではないでしょうか。
坐禅で呼吸の数を数える時の、「ひとーつ」と唱えて、その時やるべき事、相手と一つとなって、素晴らしい働き、仏さんの心で生活ができるように努めていきたいものです。
このようなお話をいたしました。
来月の坐禅会もどうぞよろしくお願いいたします!
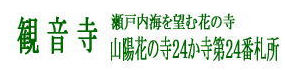



ご無沙汰しております。毎月伺いたいと思うのですが、所用とかさなってしまいます。5月は伺えると思います。楽しみにしています。いつも、ありがとうございます。
毎回のお話は、お調べになることをご自身の勉強にもなさっているのでしょうと、いつも息子を思い浮かべながら拝聴しております。素晴らしいです。
こうしてネットに残されることは、より素晴らしいです! 皆さんに、より広く伝えられますし、記録になりますね。
ますますのご精進を応援しております。
来月もよろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。いつもありがとうございます。
坐禅会で話す機会と、そのための勉強の機会を両方いただいて有り難いなあと感じております。
皆様と共に精進していけますよう、これからも頑張ってまいります。
コメントをいただいて、大きな励みになりました!
来月もよろしくお願いいたします。合掌